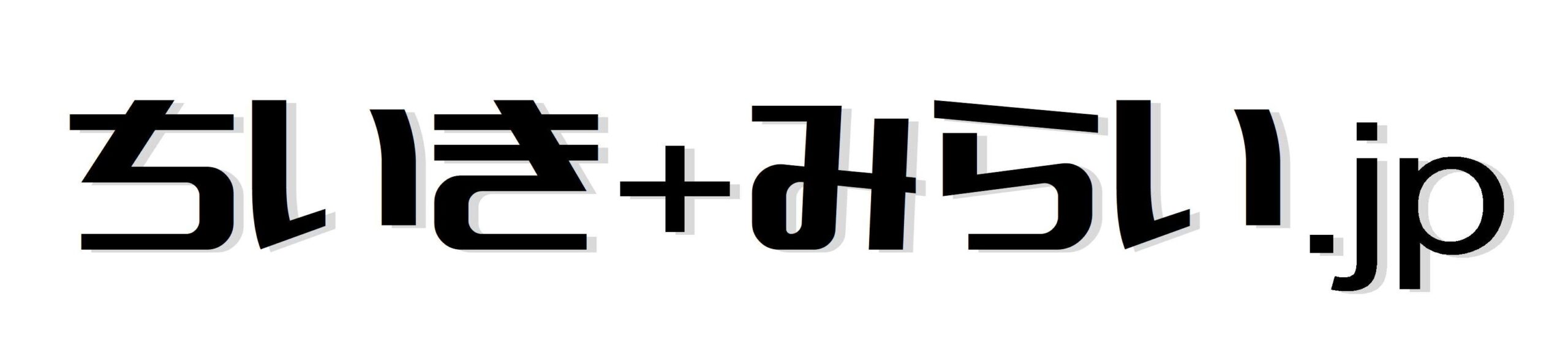1. はじめに
近年、「サステナブル」や「SDGs」といった言葉を耳にする機会が増えました。私たちの社会では、有限な資源をいかに無駄なく活用するかが大きな課題となっています。中でも、木や竹などの自然素材が「本来なら捨てられていたはずのもの」から、付加価値の高い製品へと生まれ変わる動きが注目を集めています。
その新しい発想が、「アップサイクル」です。従来の“廃棄”の価値観を大きく変える、次世代のモノづくりの考え方をご紹介します。
2. アップサイクルとは?
「アップサイクル」とは、廃棄されるはずだった素材や製品に新たなアイデアや技術を加え、元の素材よりも高い価値を持った新しい製品として生まれ変わらせる取り組みです。
従来の「リサイクル」(recycle)は、例えばペットボトルから繊維を作るなど同じ用途や価値まで戻す使い方が主流ですが、アップサイクルでは元よりも魅力あるモノやデザインに“進化”させることがポイントです。
これまでの大量生産・大量消費のリニア・エコノミー(直線型経済)から、資源の循環・廃棄量抑制のサーキュラー・エコノミー(循環経済)への転換が必要とされており、持続可能な社会の構築や廃棄物削減の取り組みが求められる現代において、その解決策としてアップサイクルやリサイクル技術が注目されています。。
3. どんな素材がアップサイクルできる?
多様な素材・分野でアップサイクルの取り組みが進んでいます。
- 繊維・衣類
古着や余剰繊維から新しいファッションアイテムやバッグ、リメイクウェア、繊維糸など。 - プラスチック
海洋廃棄プラスチックや産業廃棄物のプラ素材を、美しい雑貨やデザイン家具、建材にアップサイクル。 - ガラス
廃ガラス瓶や窓ガラスを再生し、タイルやアクセサリー、アート作品に。 - 金属/工業端材
工場の金属端材や廃車部品がアートオブジェ、家具、日用品などに変身。 - 食品ロスのアップサイクル
規格外野菜や余剰食材をスープやレトルト、動物飼料、肥料などに活用。
このように、あらゆる素材が「捨てる」を起点としない“価値創出”の対象になっています。
4. 森林の未利用材とアップサイクル
「未利用材」とは、間伐材・枝・根・倒木・端材・規格外の竹など、森林で生まれても通常の流通や利用から取り残されてきた資源のことです。
こうした未利用材が多く発生する理由には、採算性や加工の手間、流通コスト、素材の規格外による需要低迷など、さまざまな壁がありました。
しかし、「アップサイクル」という視点を加えることで、これら従来は“捨てるしかなかった”木材や竹も、クリエイティブな発想と技術によって地域や社会に新しい価値を生み出せるようになっています。
5. 木材・竹など自然素材のアップサイクル事例
森林の端材や未利用材のアップサイクルには、さまざまな事例があります。
木の端材 → 木粉 → バイオプラスチック製品
例えば製材工程の端材やおがくずを粉砕・乾燥し、木粉に加工。その木粉をバイオプラスチックの素材として配合することで、ごみ箱・トレー・食器・カトラリー・うちわなど全く新しい日用品やエコグッズに生まれ変わります。

木や竹などの植物資源を粉砕加工した品質の高いパウダーと樹脂を混合した植物由来の優しい食器
間伐竹材 → 竹粉 → 雑貨やアパレル材料へ
たけのこ生産の過程で発生する竹の未利用材も同様に竹粉として再生され、インテリア雑貨やガーデニング資材、バイオヴィーガンレザーなど多彩に展開されています。

竹活用バイオヴィーガンレザー「バンブレナ」のお財布
無垢のまま個性として活かす木製雑貨・家具・オブジェ
大きさや形の不揃いな端材・木片・枝や役目を終えた木製什器などは、その木が持つ個性を活かして、世界に一つだけのオブジェや、アクセサリー・文房具など、温もりあるオリジナル雑貨やプロダクトにもアップサイクルされています。

味噌蔵の樽材をサーフボードに加工(アップサイクル・コンテスト2019で世界3位に!)
-
地域を巻き込む実践例
たとえば徳島県那賀町では、地元の未利用材や廃棄されていた竹林資源を使い、有名イベント会場のごみ箱やノベルティ、ふるさと納税返礼品としてもアップサイクル製品が採用されるなど、次世代の循環型社会に貢献しています。

那賀町の未利用木竹材から生まれたごみ箱(大阪・関西万博にも導入)
6. アップサイクルが生み出す価値とメリット
アップサイクルの広がりは、次のような多くのメリットをもたらしています。
資源の有効活用・環境負荷低減
捨てられる資源を最大限に生かすことで廃棄物の削減・二酸化炭素排出の抑制にもつながります。
地域経済・新たな産業の創出
地元で生まれる未利用資源を使って新しい製品やサービスが生まれ、雇用や産業の創出にも結びつきます。
独自性あるブランド形成と新しい文化
一点モノのストーリーや地球にやさしい素材を活かすことで、消費者の共感を呼び、商品や企業の付加価値向上にもつながります。
7. まとめ:「アップサイクル」はだれでも、どこでも、未来をつなぐ方法
今や「アップサイクル」は、モノづくり企業や作家だけでなく、自治体や学生・一般消費者にも広がりをみせています。
使い終わったら捨てるのではなく、「どう生かすか」を考えることで、誰もが参加できるサステナブルな社会づくりが可能です。
地域に眠っている未利用材などの資源が、意外な形でアップサイクルできるかもしれません。
8. 参考事例:さらに学ぶ
森林の未利用材をアップサイクルし、社会や地域とのつながりを作りながら新しい価値を生み出す企業として、徳島県の株式会社那賀ウッドも注目されています。
「アップサイクル」に興味をお持ちの方は、ぜひ地域や素材の特性を活かしている企業の取り組み、オリジナル商品、セミナー・体験イベントなどにも参加してみてください。
あなたの暮らしと未来に、新しい価値をつなぐヒントがきっと見つかるはずです。
【用語集】
- アップサイクル:廃棄物からより価値あるものへと生まれ変わらせること。
- 未利用材:本来利用されていない資源。林業や農業、工業等で発生する端材・規格外素材など。
【参考リンク】
アップサイクル技術展@大阪 https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=44955
株式会社那賀ウッド https://www.nakawood.co.jp/
未利用木竹材のアップサイクル方法 https://www.nakawood.co.jp/jigyo/upcycle/